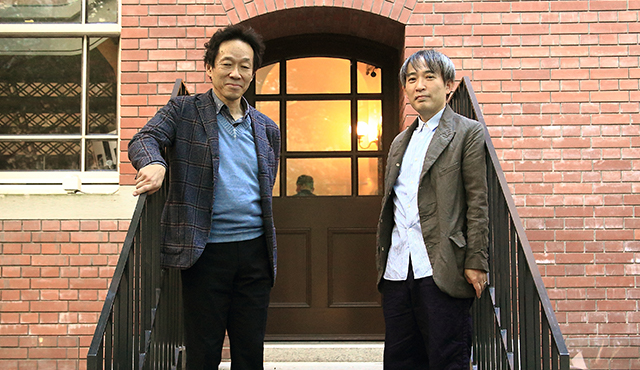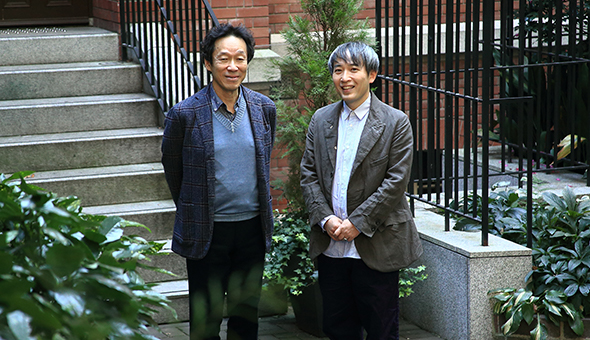館長対談
館長対談 vol.19
ゲスト
小野正嗣さん
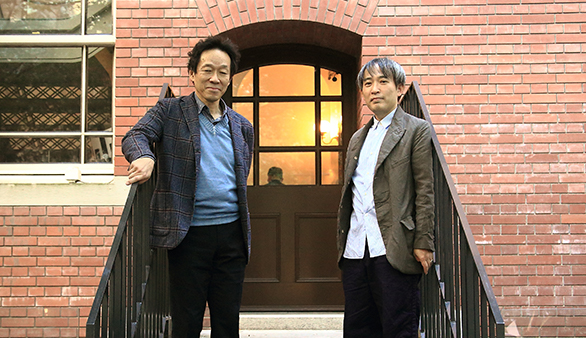
何かに夢中になっている子どもの姿に、ぼくたち大人たちは吸い込まれる
— 小野正嗣
ぼくは宙を見つめる猫に吸い込まれる(笑)
そういう夢中になる瞬間って、なかなか大人はもてなくなってくるから
— 高橋館長
小野「精神分析の父」といわれるフロイト(1856-1939)は、子どもにも性的衝動(リビドー)を含めた無意識の欲望があるという言説を提示しましたよね。
高橋ええ。フロイトが言及したような子どもの姿は、ヴァロットンの作品のなかによく見られます。たとえば、本展にも出品される当館所蔵の木版画では、警官に連行される一人の男の周りに子どもたちが集まって、はやしたてている様が表されています。そのタイトルが秀逸なんですよ。
小野どんなタイトルなんですか?
高橋《可愛い天使たち》。ちょっとゾクっとさせられるでしょ。
小野これは子どもたちが皆、無表情なのが怖いですね。小さい子どもってみんな声が似ていると思いませんか? 「パパ!」ってよその子に呼ばれて、間違えて振り返ってしまうことはよくあります。まだ「個」になりきっていない状態。何者にでもなれる可能性を秘めているということは、極端に言えば善にも悪にもなれるということでもある。それは一種の希望でもあり、恐怖にもなり得る。

フェリックス・ヴァロットン《可愛い天使たち》
1894年 木版/紙 三菱一号館美術館蔵
高橋小野さんは、お子さんは何人いらっしゃるんですか?
小野5人です。
高橋おお、それは子だくさんだ!
小野ええ、女の子が4人で男の子が1人です。日々、思うようにならない子どもという存在に苦しめられています(笑)。
高橋ぼくは一人っ子で、かつ子どももいないので、小さい子にどう接していいか、結構わからないときがあるんですよ。まあ、自分が子どもになりきってしまうと、逆に全然問題ないんですけれどね。
小野高橋館長は、大きな子どもみたいなところがありますからね、大丈夫ですよ、そのままで(笑)。
高橋妻にも「あなたは自分が子どもみたいだからいいのよ」ってよく言われるんだけれど……。やっぱりそうなのか……?!ところで小野さんは、お子さんと接していて、何か気づかされることはありますか?
小野毎日のようにあります。子どもが汚い言葉を使ったり、言うことを聞かなかったりすると、小言を言うんですが、すぐに自分もそうだったなと思い出すんです。おのれの過去を突きつけられるというか……。自分ではいっぱしの大人のつもりだけれど、この子たちと実は何も変わっていないんじゃないかと。
高橋じゃあぼくと同類ってことですね!
小野そう。大人になれない人はいるけれど、子どもじゃなかった人はいない。だから、あまり子どもに怒ってばかりいると、罪悪感を覚えます。今日も、「めんどくさいなあ、学校、行きたくないなあ」と言ってる子を、「行きなさい!」って叱ってきたけれど、我に返れば、ぼくも「大学、めんどくさいな」とまるで同じことを言っているときがあるじゃないかと。子どもたちは常に鏡です。
高橋それじゃあ、小野さんは、5枚もの鏡に囲まれて生活されているんですね。
小野そうなんですよ。うちの母がよく言います。子どもというのは、親の悪いところが似るんだと。もうゾッとしますよ(笑)。
高橋年をとってくると、最近のことはどんどん忘れてしまうのに、昔のことはクリアに思い出したり、覚えていたりするじゃないですか。
小野えっ! そうですか、やっぱり。それ、ぼくはかねてからとても重要なことだなと思っていたんです。偉大な作家が年をとってから発表した作品には、子ども時代の光景が鮮明に、かつ美しく書かれているものが少なくない。年を重ねた芸術家が子どものことを表現したほうが、本質に迫れるんじゃないかと思っているんですよ。
高橋故郷喪失者(ハイマートロス)が、失われた自分の姿や山河を思い出したりするでしょ。それと同じように、子ども時代の失われてしまった記憶が、より鮮やかに蘇ってくるのかもしれませんね。いらないものがどんどん落ちていくから。
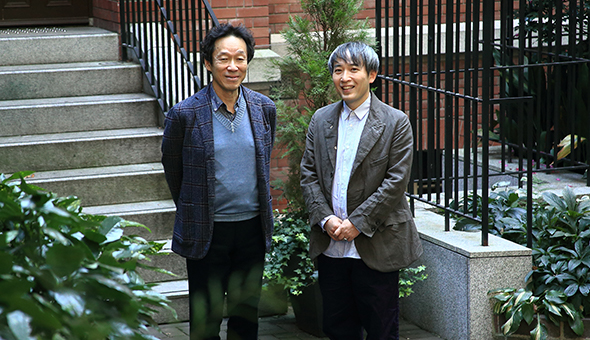
小野なるほど!故郷喪失者が自分がいま生きている現実よりも、奪われた故郷のほうが何倍も美しいと思うのと一緒ですね。
高橋言ってみれば、特定の地域の人に限らず、近代人はみんな故郷喪失者だと思うんですよ。
小野たしかベンヤミン(1892-1940/ドイツの文芸批評家・思想家)が言っていました。近代より前の時代には、ひとつの世代から次の世代へ移っても、目に映る景色はさほど変わらなかった。けれども近代になると、親の世代と子どもの世代が見る景色はまったく変わってくる。それは歴史的な背景も含めて言えることですね。
高橋ナビ派の画家たちもそういう意味では、故郷喪失者だった。
小野セーヌ県知事オスマンのパリ改造によって、19世紀のパリはドラスティックに変わった。とくに都市に住んでいたフランスの近代人たちは、かつての10年、20年で起きたこととは比較にならないほど、大きな変化の波を体験したわけですから。
高橋そういう意味では、かつてない変革期を生きる我々もまた故郷喪失者です。親が見ていたものは、絵画や写真などのイメージを使わない限りほとんど共有できない。今回の「こども展」では、絵のなかにかつての自分の姿、つまりは失われた心の故郷を見つけられるかもしれません。
小野ほんとうにそうだと思います。特に今回の展覧会で高橋館長おすすめの出品作はありますか?
高橋小野さんはロンドンでもご覧になっているかもしれませんが、ボナールが撮影した写真は、とてもおもしろいです。機能としては「記録」なんですが、ボナールの絵にも共通する「記憶を喚起させる」役割を備えたような写真なんです。一瞬の記録だけに留まらない、もっと深いものが映し出されている気がします。
小野ぼくは、モンヴェルの《ブレのベルナールとロジェ》という作品に惹かれますね。子どもが二人で並んでいる光景にグッときます。
高橋押し入れから不意に出てきた子どもの頃の記念写真、みたいな感じかな。

モーリス・ブーテ・ド・モンヴェル《ブレのべルナールとロジェ》
1883年 油彩/カンヴァス オルセー美術館蔵
小野大人の姿がなく、子ども一人だけだと頼りなさすぎる。でも無防備な存在が「二人で」支え合っているところに心が動かされるのかもしれません。ヴュイヤールの後ろ向きの女の子の絵もいいですね。
高橋《赤いスカーフの子ども》ですね。ドニの《赤いエプロンドレスを着た子ども》も掛け値なく、かわいくないですか?

エドゥアール・ヴュイヤール《赤いスカーフの子ども》
1891年頃 油彩/厚紙 ワシントン・ナショナル・ギャラリ ー蔵
小野ああ、ほんと。掛け値なしです!子どもって何かに吸い寄せられて、すぐに心奪われるじゃないですか。そして、ぼくら大人の視線はその何かに夢中になっている子どもにまた吸い込まれる。子どもたちが作り出す「夢中」というボイド(真空空間)に、ぼくらは吸い込まれるのかもしれません。

モーリス・ドニ《赤いエプロンドレスを着た子ども》
1897年 油彩/厚紙 個人蔵
高橋たしかに!ナビ派の画家たちもそうだったのかも。
小野「聖母子像」は、聖なるものをアウトプットする存在。でも、夢中になっている子どもは反対で、吸引する。
高橋わかります。猫もよくあるんですよ。宙を見ているような、いわゆるボイド状態が。そんなとき、ぼくは猫に吸い込まれている(笑)。そういう瞬間って、なかなか大人はもてなくなってきていますよね。
小野だから、そういう瞬間を留めた絵を見ると、癒やされたり、安心したりするのかな。
高橋一方で、ぼくみたいな“初老”には、絵に描かれた子どもたちとの共通項も見い出せるかもしれない(笑)。それもまた、楽しい。
小野いい展覧会になりそうですね。老若男女にぜひ見てもらいたい。ぼくもとても楽しみにしています。

小野正嗣
作家・フランス文学者
1970年大分県生まれ。東京大学大学院を経てフランス・パリ第8大学で文学博士号を取得。2001年『水に埋もれる墓』(朝日新聞社)で朝日新人文学賞を、02年に『にぎやかな湾に背負われた船』(朝日新聞社)で三島由紀夫賞を受賞。15年『九年前の祈り』(講談社)で第152回芥川賞を受賞した。18年より『日曜美術館』のキャスターを務めている。

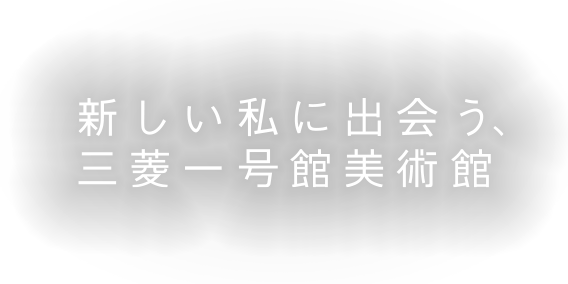







 Ticket
Ticket
 BLOG
BLOG