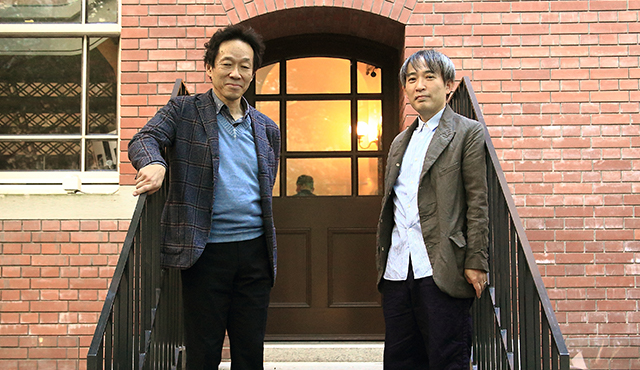館長対談
館長対談 vol.19
ゲスト
小野正嗣さん
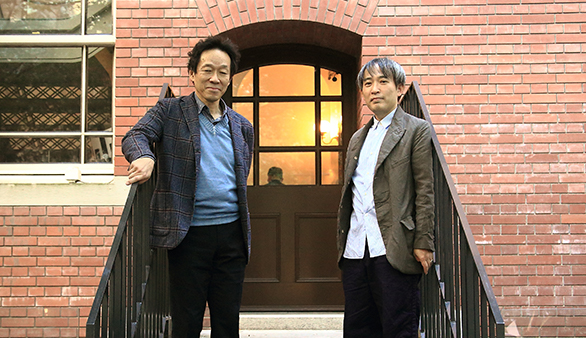
絵のなかに生きる子どもたちの煌めき
2018年からEテレ『日曜美術館』のキャスターを務められている芥川賞作家の小野正嗣さん。「開館10周年記念展 画家が見たこども展」のための館長対談は、子どもを主人公とした作品も上梓されている小野さんをおいてほかにはいないと、満を持してのご登場です。小野さんと高橋館長によって縦横無尽に繰り広げられる対談は、骨太かつ笑いの絶えない時間となりました。

ナビ派の画家たちは、絵画の主題として子どもを積極的に取り上げた集団
— 高橋館長
ナビ派の画家たちがそんなに、子どもの絵を描いているとは知りませんでした
— 小野正嗣
高橋2018年に当館で開催した「ルドン展―秘密の花園」の際には、『日曜美術館』で取り上げていただき、お世話になりました。反響もとても大きかったんですよ。ありがとうございました。
小野ルドン展をご紹介したあの『日曜美術館』は、ぼくが司会をするようになった初回だったんです。お客さんがいない時間に《グラン・ブーケ(大きな花束)》を中心にした装飾画の全貌を鑑賞させていただいた貴重な体験は忘れられません。素晴らしい時間でした。ぼくも、とても印象に残っている展覧会です。
高橋あれからもう2年。三菱一号館美術館は2020年4月に開館10周年を迎え、2月15日からは10周年記念として「画家が見たこども展」が始まります。今回の館長対談では、『獅子渡り鼻』(講談社)など、子どもが登場する小説もご執筆されている小野さんとぜひお話ししたいと思って、お招きしました。
小野ありがとうございます。10周年記念展のテーマとして、なぜ「子ども」を選ばれたんですか? ちょうど子どもが10歳になったお祝いという感じでしょうか?
高橋たしかに10歳なので、そんな感じももちろん含んでいます。今回の展覧会は、南仏にあるボナール美術館との共同主催なんです。当館が開館した翌年の2011年、ニースから少し西に行くと映画祭で有名なカンヌがあります。ル・カネはそのカンヌの背後の丘に広がる小さな町です。そこにボナール美術館がオープンしました。ル・カネにはボナールが晩年に過ごした家とアトリエが残っていて、近年新築の美術館が建てられたんです。一号館とほぼ同じ時期にオープンした美術館であり、ナビ派は当館のコレクションとも親和性が高いため、以来、ボナール美術館とは交流を続けてきました。いつか一緒に展覧会を企画したいと思っていたところ、この10周年がいい節目の機会だなと。ボナールをはじめナビ派の画家たちは、絵画の主題として子どもを取り上げた集団なんです。これまで、あまり注目されてこなかったテーマなので、ぜひ「子ども」でいきましょうということになりました。
小野昨年の2月、イギリスのテート・モダンで開催されたボナール展を見たんです。そこでボナールが撮影した子どもの写真が出品されていて、驚いたばかりです。ナビ派の画家たちがそんなに「子ども」を視野に入れた創作活動をしているとは、知りませんでした。
高橋そうなんですよ、一般的には知られていない側面だと思います。そもそも、ルネサンス期以来ずっと、こどもは一人前の人間とはみなされなかったので、まともな絵の主題に描かれることもほとんどなかったわけです。動物とニヤイコールの存在でしかない。印象派の画家たちでさえ、子どもの姿は描いてはいるものの、一種の「かわいい付属物」として子どもをとらえています。一方ナビ派の画家たちは、子どもや動物を主体的に描きました。子どもを展覧会のテーマに据えることで、これまでとは違うアプローチでナビ派の画家たちに光を当てられると思っています。
小野最近、メディアなどで子どもが取り上げられるときには、いじめや児童虐待、貧困率の高さなど、ネガティブな話題が多い気がします。でも絵画には、子どもたちの、生そのものの輝きといったポジティブな側面が描かれていて、この時代だからこそ、開催する意義が大きい展覧会だと思います。もちろん、子どもは、決して純粋なだけの存在ではないですよね。ちょっと意地悪な面もあって、決してわかりやすい存在ではない。けれども絵には、そうした側面も含めて、暴力的ではない表現で子どもの本質が描かれているのではないかと思います。19世紀末から20世紀、つまり今からだいたい100年前の子どもたちが絵画のなかでどのように表現されているかは、とても興味がありますね。文学では、19世紀というと、ディケンズやドストエフスキーといった作家が苦しい境遇にある子どもの姿を著していますが、絵画ではどうなんですか?
高橋ナビ派よりも少し前の時代のロマン主義の画家たち、たとえばドラクロワの《民衆を導く自由の女神》には、女神の傍らにガヴローシュ(ヴィクトル・ユゴー『レ・ミゼラブル』に登場するパリの路上で生活する少年)みたいな子どもが描かれています。

小野おお、ガヴローシュですか!苦しい境遇のなかでもしたたかに生きている子どもの典型ですね。ナビ派の画家たちの作品にはどんな子どもたちが登場するんでしょう? ナビ派というと、装飾的なモティーフや日常を切り取った親密な作風は思い浮かびますが……。
高橋ナビ派の作品は、平面的、装飾的というキーワードで説明されることが多いのですが、それを言い換えると「絶対自由という視点で造形を見た画家たち」と表すことができると思うんです。
小野「絶対自由」とは?
高橋歴史画を頂点とするアカデミックなヒエラルキーや造形的な約束事から自由になった人たちと言ったらわかりやすいですかね。ルネサンスの時代から西洋の画家たちは、三次元の現実をいかに二次元に変換するかに腐心してきました。西洋美術はそうして近代まで脈々と歴史をつないできたわけです。でも、マネや印象派の画家たちが活躍する近代になって、その伝統が崩壊し始めました。さらにナビ派の画家たちが登場する頃になると、絵画の二次元性、つまり平面性に着目されるようになります。そして平面性を目指すというのは、単に造形的なことだけを指しているのではなく、テーマも同様なんです。つまり、これまで主たるモティーフとして描かれてきたものと、背景に描かれていた、いわゆる装飾的なサブのモティーフの境もなくなっていく。彼らの絵画が装飾的と言われるのは、こうした理由もあるわけです。
小野なるほど。それまで伝統的な西洋絵画で描かれてきた子どもの代表といえば、聖母子像のイエスで、それは宗教的な意味を強く帯びたモティーフだった。でも、身近な日常に暮らす子どもの姿も、意味ある存在として描かれるようになったわけですね。ナビ派の画家たちは、すべてのモティーフを造形的にもテーマ的にも等価値として見つめた。たしかに絶対自由だ、とてもおもしろい!
高橋小野さんも、作品のなかで子どもたちに何かの役割を仮託させることはありますか?
小野そういう意識はあまりないですね。けれども、高橋館長の「絶対自由」という言葉が象徴するように、ぼくは、子どもは大人になる前の「可能性」そのものを体現する存在だと思っています。何者にも成り得る存在ですね。それなのに、彼らの絶対的な可能性や自由が失われていく、断ち切られているという社会の現象には、書き手として興味があります。『獅子渡り鼻』もそうした興味が執筆の契機の一つになりました。
高橋子どもは、どうしても社会的弱者になりやすい。
小野ええ。哺乳類のなかでも人間の赤ん坊は、圧倒的に無防備です。イギリスの小児科医・精神科医のドナルド・ウィニコット(1896-1971)がたしか言っていますけれど、馬や牛は生まれてすぐに自分で立てるのに、人間の子どもは、すぐそばに大人、母親的な存在がいないと生きていけない。人間は個ではなく、必ず複数なんですよね。我々は子どもを通して、動物としての人間の弱さを見せられているのかもしれない。だからこそぼくたちは、小さな子どもが働いている児童労働などの現実を目にするとかわいそうだと感じる。それは、彼らが弱者であり、かつ手にしているはずの自由が奪われていることにショックを受けるからです。そして大人になることが、あらゆる可能性を捨てていく道程であることも知っているから、もう二度と我々が戻ることができない子どもという存在に対して、時に憧憬やノスタルジーを抱くのだと思うんです。

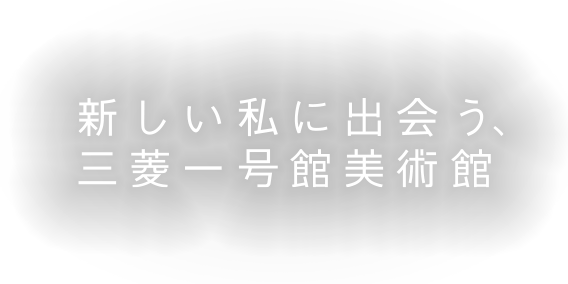







 Ticket
Ticket
 BLOG
BLOG