館長対談
館長対談 vol.17
ゲスト
生駒芳子さん

極上の美しい夢を見せてくれるのが
ファッションの展覧会の魅力
— 生駒芳子
ぜひフォルチュニの“美の神殿”に
迷い込んでみてください
— 高橋館長
高橋フォルチュニの名を一躍世に知らしめたドレス「デルフォス」は、ウエストをしぼらないドレスです。こうした体を締め付けないスタイルは、フォルチュニが最初と言っていいのですか?
生駒20世紀初頭、コルセットから女性を開放するドレスが登場しました。その双璧が、フォルチュニとポール・ポワレ(1879-1944)です。ポワレは生粋のパリジャンで、ファッションの王様といわれています。コルセットを使わないハイウエストのドレスを発表して、欧米のファションに革新をもたらした存在ですね。
高橋アール・デコの到来とともにパリを中心に活躍したポワレは、当時の世界のファッションシーンを席捲した存在ですよね。それに比べるとフォルチュニは、より個性的な人々に愛された感じがします。例えば、ペギー・グッケンハイム、イサドラ・ダンカン、スーザン・ソンタグ、イダ・ルビンシュタインといった顧客がいました。
生駒プリーツを活かした「デルフォス」は、もともとは室内着として作られたのかもしれません。また、当時って船旅の時代でしょ。きっと船旅の時、富裕層に重宝されたのではないかしら。つまり、プリーツであれば、くるくるっとたためて小さくなる。船旅にもとても便利です。ポワレは晴れの場で着用するためのイヴニング・ドレスを多く作っていたので、目立つのかもしれませんね。でも、フォルチュニの「デルフォス」は、美しさと機能性の見事なマリアージュだと思います。
高橋たしかに、美と機能性の融合は、近現代のキーワードですね。
生駒だから、とてもモダン。そして、その時代、室内着を作り続けたってすごいことだなと思うんです。現代でこそ、アウターとインナーの区別がなくなってきています。たとえば、Tシャツも1世紀前は下着で、見せてはいけないものだった。この時代に室内着を極めたって、かなり先見の明がありますよ。凡人ではできない!
高橋そうそう、顧客といえば、現代美術家の森村泰昌さんがセルフ・ポートレイト作品でフォルチュニのドレスを使ったとおっしゃっていました。
生駒きっとアーティストの創造力を刺激するドレスなんでしょうね。プリーツという素材を選んだフォルチュニは、おそらくドレスをデザインするというよりも、オブジェを作っている感覚だったんじゃないかしら。フォルチュニは光フェチだったと聞いています。つまり光と影の芸術、陰翳礼讃です。
高橋光と影ですか。そう考えると、舞台装置や照明に力を入れていたこともうなずけますね。
生駒フォルチュニの作品が装飾を排した現代風なセンスの原点であることは紛れもない事実でしょう。その後、バイアスカットの女王と呼ばれるフランスのデザイナー、マドレーヌ・ヴィオネ(1876-1975)なんかが出てきて、幾何学的、抽象的なミニマルなラインが完成されていきました。そうしたデザイナーに共通しているのが、日本からの影響です。ヴィオネも日本の着物から強い影響を受けていますし、フォルチュニも中国や日本の絹を使っているわけですよね。お父様の影響もあるだろうし。
高橋日本の型紙なんかもたくさんコレクションしていたようですよ。
生駒伊勢型紙ですか?
高橋ええ、お父さんのコレクションは解体してしまいましたが、フォルチュニ自身のコレクションもかなりの量があるので、今回の展覧会でも一部が出品される予定です。

生駒実は日本ってファッション大国なんですよね。私も日本の美をもっと発信したいという思いが募って、日本の伝統工芸をベースにしたHIRUME(ヒルメ)というブランドを立ち上げてしまいました。今日着ているこのスカジャンも、加賀繍を使ったものなんです。若い才能もどんどん世界に羽ばたいています。それは、今に始まったことではなく、高田賢三さん、三宅一生さん、山本耀司さんや川久保玲さんらが欧米のファッションに切り込んでいって、道筋を作っていきました。そして今、彼らの子ども世代が育ってきています。たとえば、ANREALAGE(アンリアレイジ)というブランドを立ち上げた森永邦彦さんは、モエ・ヘネシー・ルイ ヴィトン(LVMH)が、若手デザイナーの支援のために創設した「LVMHヤング ファッション デザイナー プライズ」の2019年のファイナリストに日本から唯一選出されました。彼もまたフォルチュニのように、ファッションの領域を超えて、デジタルアートや音楽を使ったり、光で模様が浮かび上がるようなドレスを作ったりして、世界的に注目されています。日本人の美意識ってすごいなと改めて感じます。
高橋それは嬉しいニュースですね。
生駒森永さんは地道な努力を重ねて、美しい世界を追求し続けています。フォルチュニもそういう人だったんじゃないかと私は思うんです。結果として女性をコルセットから開放することになりましたが、フォルチュニはただ美しいものを追求しただけ。その結果、ドレスという概念そのものに革命をもたらすことになったのではないでしょうか。
高橋フォルチュニはプリーツの技法を秘密にしていたらしいけれど、それも儲けやビジネスとは関係なくて、ただ自分の美を守りたいだけだったのかもしれませんね。
生駒ファッションはビジネスやマーケティングと切り離すことができない産業です。着る人、つまり顧客がいないと完成し得ないものですから。だから、フォルチュニのように極めて個人的な美への思いだけでファッションに携われる人って今はなかなかいない。彼は自分の“美の神殿”に住み続けることができたとても幸せな人だったんじゃないかしら。
高橋今回の展覧会では、そんな彼の “美の神殿”に迷い込んでいただきたいと思います。最後に、生駒さんからファッションの展覧会の楽しみ方を読者の方にアドバイスいただけますか?
生駒私にとってファッションは、夢を与えてくれるもの。そして極上の美しい夢を見せてくれるのがファッションの展覧会だと思います。とにかく1着のドレスにうっとりして、ご自分の目で夢の世界にトリップしていただきたい。そして、これを着たら自分はどんな感じかしら? このドレス着ていた人はどんな生活を送っていたのかしら? とか、夢想してみるのも楽しいです。
高橋ファッションって、人間と極めて距離が近い表現領域ですよね。絵画とは違って、人間が着て、動くことで初めていきてくる。つまりフィックスしていない。これまで美術館は、静的なものを扱うという既成概念がありました。けれども、動きや時空の飛躍は、人間の想像力でカバーするという展覧会の楽しみ方があってもいいわけです。
生駒はい、まさにファンタジー。三次元だけれど、見る側の姿勢ひとつで、四次元や五次元にも入っていけるんですよね。
高橋フォルチュニをご存じない方や若い方にも、必ずや楽しんでいただける展覧会になると思います。
生駒フォルチュニのクリエイションが発する「美しいものは永遠」というメッセージが、多くの方に届くことを私も願っています。きっと私は、ひたすらうっとりと、ため息をつき続けていることでしょうね(笑)。

生駒芳子
ファッション・ジャーナリスト
兵庫県宝塚市生まれ。東京外国語大学フランス語学科卒業後、編集プロダクションを経て、フリーランスのライターとして雑誌、新聞でファッション、アートに関する記事を執筆。1998年、『ヴォーグ』日本版の創刊時に副編集長として就任。その後『エル・ジャポン』『マリ・クレール』日本版の編集長を歴任。2008年11月に独立後はフリーランスのジャーナリスト・エディターとして、ファッション、アート、クール・ジャパン、ライフスタイル、社会貢献、エコロジーなどに関する活動を広く展開している。現在は、伝統工芸をベースにしたファッション&ジュエリーのブランド「HIRUME」(https://www.hirume.jp/)をプロデュース。

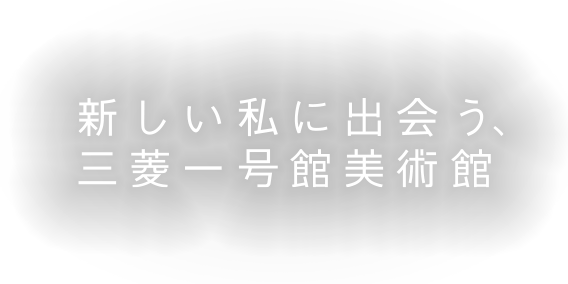







 Ticket
Ticket
 BLOG
BLOG





