館長対談
館長対談 vol.17
ゲスト
生駒芳子さん

“美の神殿”に住み続けたフォルチュニ
『ヴォーグ』や『マリ・クレール』日本版の創刊時から、長くファッション誌の第一線で活躍されてきたファッション・ジャーナリストの生駒芳子さん。その生駒さんが「ファッション界のレオナルド・ダ・ヴィンチのよう」と称するのがマリアノ・フォルチュニです。そのミステリアスな魅力をぞんぶんに語っていただきました。

フォルチュニのデザインは時代を軽々と超えて、
不思議な吸引力で人々を魅了します
— 生駒芳子
今回の展覧会では、ファッションや染織を軸に、
フォルチュニの多岐にわたる活動をご紹介します
— 高橋館長
高橋本日はようこそおいでくださいました。生駒さんには3年前に当館で開催した「PARIS オートクチュール――世界に一つだけの服」展の際、音声ガイドでたいへんお世話になりました。
生駒オートクチュール展に続くファッションの展覧会、それも私の大好きなマリアノ・フォルチュニ(1871-1949)の展覧会を開催されるとうかがって、今日は飛んで参りました!
高橋でも、フォルチュニって、一般にはあまり知られていない存在ですよね。
生駒フォルチュニは、服飾だけでなく舞台芸術や照明のデザインなども手がけていて、相当にマルチな才能の持ち主だったようですね。活躍の割にその名が知られていないのは、ファッションの領域にとどまらない広範な活動ゆえかもしれません。
高橋馴染みの薄い読者の方に向けて、少しフォルチュニの経歴を紹介させてください。ヴェネツィアを拠点に国際的に活躍したフォルチュニは、繊細なプリーツを施した絹のドレス「デルフォス」で、20世紀のファッション界で名を馳せたデザイナーです。プロフェッショナルではなかったものの、写真も撮っていて、それもなかなか味があっていい。また、ワーグナーが大好きで、舞台デザインや演出も手がけ、先端テクノロジーにも関心がありました。モダンなデザインの照明器具や新しい製法の絵の具の開発なんかもしています。今回の展覧会では、ファッションを軸に、フォルチュニの多岐にわたる多才な創作活動をご紹介する予定です。
生駒フォルチュニといえばスタイリッシュなドレス「デルフォス」がすぐに思い浮かぶけれど、それ以外の作品も拝見できるのは、とても楽しみです。
高橋じつは、以前当館で開催したプラド美術館展(2015年10月10日〜2016年1月31日)で、フォルチュニのお父さん(マリアノ・フォルトゥニ・イ・マルサル/1838-74)の油彩画が出品されていたんです。そこに3歳のフォルチュニも描かれています。父親のマルサルは、19世紀スペイン美術界の巨匠。国際的な名声を博した画家でした。日本美術の熱心なコレクターでもあり、プラドの作品も日本風の広間で寛ぐ子どもたちの姿が実に洒脱に活写されています。
生駒お父さんもかなり前衛的だったんですね。それにしても、いかにこの時代、日本美術がヨーロッパに影響を与えていたかがよくわかります。
高橋作品が描かれたのは、パリで第1回印象派展が開催された年(1874年)。そして、これが父親の絶筆となりました。描法といい、ジャポニスムのモティーフといい、進んでいるでしょ、かなり。

生駒ほんとうに。ということは、フォルチュニは、いいおうちのお坊ちゃまだったということですか?
高橋はい、超売れっ子画家の息子ですからね。3歳のときに父親が亡くなると、家族でパリやローマに居を移します。そしてフォルチュニが18歳の頃、母親は体の弱い息子のために、ヴェネツィアへ移住しました。母親もまた、スペイン王室に縁の深い画家一族、マドラーソ家の出身でした。
生駒そこで、ヴェネツィアが出てくるんですね。でも、体が弱いとどうしてヴェネツィアなのかしら?
高橋なんでも、馬の尻尾(毛)アレルギーだったとか。ヴェネツィアは今も島内に車は乗り入れできませんが、当時から馬車もダメだったので、フォルチュニにとって快適に暮らせる土地だったんでしょう。
生駒まぁ、そんなアレルギーがあるんですね。それがフォルチュニの未来に大きく影響してくるなんて、人生ってほんとうに不思議。
高橋フォルチュニは、仕事をしていくうえで、ヴェネツィアという土地を戦略的に利用していたのではないかと私は想像しているんです。18世紀末、ヴェネツィア共和国はナポレオン軍の侵攻によって、その栄光の歴史に幕をおろしました。しかし、半世紀後、イギリスの美術批評家ジョン・ラスキンが著した『ヴェネツィアの石』(1851-53)がヨーロッパ中でヒットするなど、歴史ある水都ヴェネツィアの魅力に再び光が当たり始めます。1895年には国際的な現代美術展であるヴェネツィア・ビエンナーレが、やがて1932年にはそのビエンナーレの一貫として現在のヴェネツィア国際映画祭も始まりました。ヴェネツィアが都市として再生していくさなかに、我らがフォルチュニもこの地にいたというわけです。彼はミステリアスなヴェネツィアのイメージをうまくビジネスに使っていたんじゃないかと思うんですよ。
生駒あえてパリではなく、ヴェネツィアに拠点をおいたというところが意味深です。
高橋生駒さんは、ヴェネツィアにはどんなイメージをお持ちですか?
生駒大学の同窓生がヴェネツィア大学で教鞭をとっているので、よく行きますし、とても親しみを覚える地です。上陸しただけで陶酔感があって、人をうっとりとさせる場所。海につながっている水の都だから、異次元への入り口という感じがするんです。カルナヴァーレ(カーニバル)もあるからでしょうか? 手を伸ばせば別世界へ行けるような、マジカルな街というイメージ。私のなかで、そんなヴェネツィアの雰囲気とフォルチュニの世界観はぴたりと重なるんです。両者ともに熟れきっていますもの。一方で、フォルチュニのデザインは、今回の展覧会のコピーにあるようにまさに「100年たっても、新しい」。ミステリアスでありながら、カタチがここまで古びないって、なかなかないことですよ。時代を軽々と超えて、不思議な吸引力で人々を魅了する。そんな世界観もヴェネツィアの街と、とても似ているような気がします。

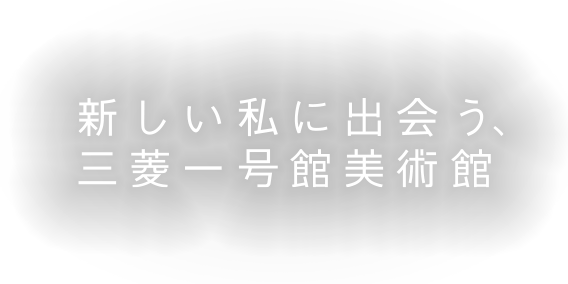







 Ticket
Ticket
 BLOG
BLOG





