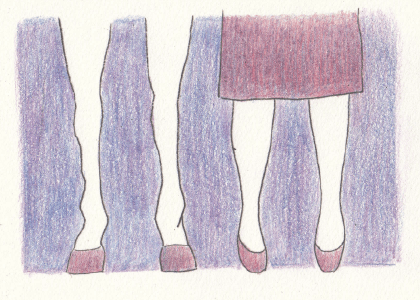そこにいる私 3
私と出会う
私は何になりたいのだろう。私は何になりたかったのだろう。若いときも、大人になってからも、私はそんなことを考えていた気がする。いくら考えてもうまく答えが出なかったから、とくべつな努力もせず、野心を持つこともなく、そのときそのときに最善だと思う方向に慎重に足を踏み出して過ごしてきた。だから、こうなるだろうという予想を大きく外れるようなことにはならないはずだったし、波乱とは無関係の日々になるはずだったのに、私は今、以前には思いもしなかったようなところにいる。
四十歳を過ぎて私は油絵を習いはじめた。気づかなかっただけで父から絵の素質を受け継いでいて、母の英才教育も意味があったかもしれないと思ったのだ。絵を描くことはたのしかったけれど、残念ながら、私に素質はなかった。ないと気づいたのは、その絵画教室に、ずば抜けてすごい絵を描く人がいたからだ。まだ中学生の男の子で、たった一色の水彩絵の具で木を描いても果物を描いても、独特の世界をそこに出現させる。私は彼の絵を見るのが好きだった。次第に、自分の絵の上達ではなく、彼の絵を見るために教室に通い続けた。
高校生になると、彼の絵はいくつかのコンクールで受賞するようになった。彼が美大に進学し、絵画教室をやめると私もやめて、個人的に応援をし続けた。絵では食べていけないから就職すると言う彼に、あなたには才能がある、絵を続けるべきだと説得をし続け、彼の絵を持ってギャラリーをまわり、ちいさな個展を開くところまでこぎ着けた。私は彼の、個人秘書でもありパトロンでもあった。パリの夜、ひとりで歩いていけるようになりたいと私は発見するように思ったが、彼の絵のために何かをしているとき、まさに、自分の足で軽やかに歩いている、という実感があった。
彼の才能が世間に認められはじめると、私は退屈を覚えるようになった。そのときには、私は自分がやりたいことに気づきはじめていた。私は本物の芽をだれよりも早く見つけて、それを芽吹かせたいのだ。絵画でなくともいい、ダンスでも陶芸でも楽器演奏でもなんでもいい。もちろん私はそれぞれの道のプロではない、でも、本物はわかる、となぜか私は思いこんでいた。
本物を見つけて世界へ送り出すのには、根気も時間もお金も必要だった。家庭を顧みず、他人のことばかりに狂信的に熱心になった妻が理解できず、夫には離婚を持ちかけられた。離婚時に受け取った財産分与も他人の活動のためにつぎこんだ。
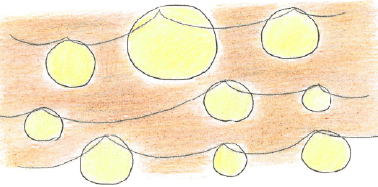
かかわった全員がその道で成功したわけではないし、ふいとその道を外れてしまう人もいるにはいた。けれどおおむね、本物を見つける私の目はたしかだった。もう人生も終わりに近いというのに、ちいさな賃貸住宅に住み、家族もおらず、財産もない。若き日に、こんな人生を望んだことは一度もなかったし、想像すらしたことがない。それでも私は、願ったとおり自分の足で歩きまわることができたと思っている。その足で、いきたい場所にたどり着いたと思っている。世界に出ていった本物たちが、たとえ私のことなど忘れたとしても。
中学生だった絵の天才が、上海にオープンする美術館で個展をすることになったと、オープニングレセプションの招待状を送ってくる。これが最後の旅だと思いながら私は出かけていく。
二十年ぶりに訪れた上海は、私の記憶とはまったく異なった近未来の町になっている。招待された美術館もコンピューターグラフィックみたいだ。オープニングレセプションは夕方からなので、ホテルの近所を散策する。近未来の町でも、路地を曲がれば昔ながらのプラタナスの並木があり、古い建築物が並んでいる。フランス租界時代の建物をリノベーションしたカフェが目につき、入ってみる。明るいおもてから足を踏み入れた店内は、一瞬闇のように暗い。案内された席に座る。ようやく目が慣れてきて、店内を見まわし、私は息を呑む。
店のいちばん奥に、その絵はある。立ち上がり、私を待っていたかのようなその絵に、ゆっくりと近づく。いちばん最初の記憶にある絵。パリで再開した絵。そこにいる馬は、おそろしくはなく、かなしくもなく、ただひたすらになつかしい。そうして向かい合っていると、そこに描かれているのは、馬ではなくて私自身のように思える。鏡の前に立っている錯覚さえ抱く。きっと、過去もそうだった。この絵は私自身を映してきた。未来におびえる、まだ何ものかもわからない幼い私。自分の足で歩くよろこびを知らない私。そして今、もっともあたらしい私がそこにいる。
過ごした時間と見てきた光景と、味わった恍惚と生きるよろこびを、その体のなかにためこんで、私を見る馬はこんなにもやさしく、こんなにも孤独で、こんなにも満ち足りている。そうか、私はまちがっていなかった。この想像もしなかった人生は、間違いなく私自身のものになるべきだった。
スタッフの若い女の子が、立ち尽くす私に何か言う。こちらに席を移しましょうか? と訊いているらしい。いいえ、いいの、ごめんなさいね。私は日本語で言って、先ほどの席に戻る。手渡されたタブレットがメニュウになっている。冷たいお茶の写真を指さす。
店の奥の絵は、窓から射しこむ陽を浴びて、崇高に思えるくらい輝いている。私が笑うと、絵のなかの馬もゆったりとほほえむ。
【プロフィール】
角田光代 作家
1967年神奈川生まれ。
1990年「幸福な遊戯」でデビュー。
2005年「対岸の彼女」で直木賞受賞。
近著に「坂の途中の家」「いきたくないのに出かけていく」等。