「拝啓 ルノワール先生」担当学芸員インタビュー⑦<生きることへの情熱>
<生きることへの情熱>
梅原が関心を抱いた画家は、ルノワールだけかというとまったくそうではないですし、絵画だけにとどまらず、演劇、
食、服飾、書画骨董にも大変関心が強かった。ある意味、視界が狭い凝り固まったオタク的思考ではなくて、とても
バランスのとれた、生きること、生活そのものを楽しむことが出来る天性の才能があったと言えるのではないでしょうか。
―晩年のイメージから豪快なイメージが先行していましたが、いろいろな面があるのですね。
そうなんです。
演劇をはじめとしていろいろな分野に興味を持っていました。これは白洲正子さんが書いているのですが、梅原は老齢になってからも芝居の夢を見る事が多く、ある時はナポレオンの役で、舞台に出たところで目が覚めた、とご自身が話していたそうです。それだけ演劇に対する想いが強かったというエピソードですね。梅原は、演劇についての本もたくさん持ち帰っていたのですが、残念ながら関東大震災で焼けてしまいました。
―ちなみに演劇に対する情熱を発散させる場所はなかったのでしょうか?
それは大変いい質問ですね。僕は、梅原の著作集『天衣無縫』(求龍堂、1984年)に完結している、ルノワールの追憶の文章での筆の強さというのは、演劇的な言葉遣いからきていると思います。日本でもたくさんの演劇を見ていて、当然フランスではフランス語でセリフを理解していました。例えば忠臣蔵をフランス語に翻訳する手伝いなどをするほどにはまりこんでいたりですとか、ムネ・シュリーという役者さんの楽屋に、ヴィクトル・ユゴーの舞台の後に与謝野鉄幹と訪ねて行っています。さらに自分が帰国するときには彼の元へ帰国の挨拶に行って、写真にサインをもらったりもしています。
―それにしても、梅原さんは行動の人なのですね。
そうなんです。めちゃくちゃすごいでしょ。
アトリエに押しかける。
楽屋に押しかける。
会いたい人には、会いに行きます。
―そんな梅原さんでも会いに行けなかったドガについて気になりますね。
ドガについてはかなり強いあこがれがあって、ドガのような線描は描けない、ドガにはなれないから違う道をとったのかもしれません。
今回展示している梅原が国立西洋美術館に寄贈した《背中を拭く女》no.31は、そのような憧れの人の作品をそのまま手に入れたいという欲求から、梅原が所有していたのかもしれません。ただ、この絵は私有にするべき作品ではないなという考えから、最終的に公に寄贈したのではないかと思います。
国立西洋美術館に入れるために買ったのか、それとも所有していて最後に入れることにしたのか、その順番はわかりませんが、ああやって公のコレクションにしたというのは、大きな社会貢献です。すごいというか、なんというか人間的に大きなことをしたと思います。
次回は、いよいよ解説最後、今回のメインビジュアルにもなっている、パリスの審判についてです!
お楽しみに。
公式ブログトップへ


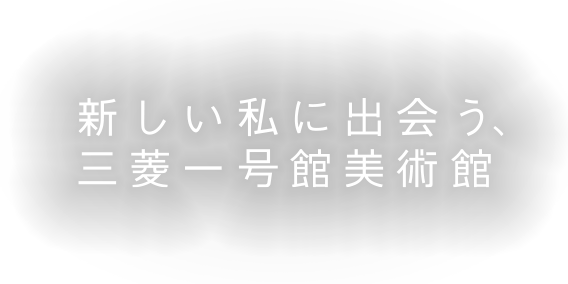







 Ticket
Ticket
 BLOG
BLOG


