山口晃さん「ルノワール×セザンヌーモダンを拓いた2人の巨匠」
画家の山口晃さんが「ルノワール×セザンヌーモダンを拓いた2人の巨匠」展をご覧になり、セザンヌ作品の魅力についてご執筆くださいました。
展覧会図録によるとルノワールは、人物像を描く時にそのモデルが喋っても動いても一向に頓着しなかったそうですが、それに対してセザンヌは、「りんごのように」長時間じっと動かないよう指示するのだそうです。
これを単にセザンヌの気質のせいにするのは間違いで、彼の絵の作りを見るとそう指示を出さざるを得ないのがよく分かります。

1875年頃の風景画「赤い屋根のある風景」では家、樹木、草地など対象ごとに筆致を変え、色を対象の形態に即するように塗っているのですが、1895年頃の風景画「赤い岩」になると、画面全体を均質なストロークで描くようになっており、そのことが色を対象の形態から部分的に遊離させていています。


その、ストロークがいくつか集まったものを彼は「プラン」と呼んだそうで、「赤い岩」では風景がプランの集合によって画面内に再構築されている様をよく確認できます。そして、各プランやプラン同士は大変厳密に色彩調整され、一部の変更でも全体の再調整が必要になるようなのです。
やはりセザンヌのモデル経験者が、動いたら「一からやり直しになる」という類のことを言われた話は、これに関係することでしょう。

その厳密な色彩調整は、恣意的にではなく実際の風景に基づいて行われます。現地に行くとこの絵のような色の岩がありますし、サント・ビクトワール山もセザンヌの絵のような色をしていることに驚かされます。
故にセザンヌの固有色への回帰とみられたりしますが、私の見立ては少し違って、あれはその場に一番長くある色を長時間露光的に捉えたものではないでしょうか。それによって画面内の色に、清新さと永続性を両有させているのです。

そうしてできた絵は、見る者の内にちょっと他にない感覚を引き起こします。
通常物を見ると物の方に色がついているよう見え、自分の目の側が色を感じている感覚にはなりません。しかし、セザンヌの絵では、プランのストロークによって画面内の物の表面から少しだけ遊離した色彩が、一瞬だけ純粋な色として自分の目の側に知覚され、すぐ後に、厳密な色彩秩序によって画面内の物の表面に収まり空間を認識させます。
その流れはあたかも、いつもは瞬時に行われる目が色彩を知覚し、風景として認識する過程を、長回しにして各段階を改めて感じさせてくるようなもので、見ている対象ではなく、普段は透明化している「見ること自体」を体感しているような感覚に導くのです。
その感覚こそセザンヌが、「サンサシオン*」と呼んだものに近似しているのではないかと、勝手に思って感動しています。
ただ、それはすぐに起こる感覚ではなく、絵の前にしばらくぼーっと佇んで、チャンネルがあった瞬間不意に、凄まじくやってきます。
あの感覚が忘れられなくて、セザンヌが掛かると足を運んでしまうのです。
*サンサシオン:感情にいたる前の感覚


公式ブログトップへ


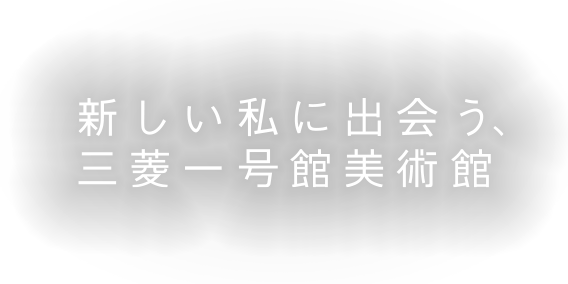







 Ticket
Ticket
 BLOG
BLOG


