坂本繁二郎 解説
坂本の描くモティーフと色に注目してみましょう。牛、馬、人物、湖、建物、林檎、能面、花…坂本の描くひとつひとつのモティーフは、独特の色調と筆致で作られており、絵画の本質的な魅力を示しているようです。新しい芸術の動向が次々と出てくる時代に、流行に惑わされず、一貫して自身の絵画を探求し続けました。39歳の時にフランスへ渡り、3年間滞在した経験が、坂本の芸術にどう影響したかを考えていきたいと思います。
坂本繁二郎 略歴
1889(明治22)年、福岡県久留米市に生まれた坂本繁二郎は、森三美に洋画の手ほどきを受けた後、学友の青木繁を追いかけるよう上京し、小山正太郎の不同舎で本格的に絵画を学びました。1921(大正10)年から1924(大正13)年までの3年間、フランスへ渡り、シャルル・ゲランに半年ほど師事しますが、言葉の問題もあり通学を止めて、ブルターニュ地方はじめフランス各地を訪れては制作して過ごしました。帰国後は東京へ戻らず、故郷にほどちかい福岡県の八女に拠点を構え、1969(昭和44)年に亡くなるまで終生ここで過ごしました。
1.《うすれ日》 解説パネル
本格的な絵画修行に勤しむも、学友の青木繁が注目を浴びる傍ら、坂本は遅咲きと言えます。1912(明治45・大正元)年の第6回文展に出品された《うすれ日》(no.1)が夏目漱石に評価され、ようやく画壇の耳目を集めます。「牛は沈んでいる。もっと言えば、何か考えている。…(中略)この変な牛を眺めていると自分もいつかこの動物に釣り込まれる。」坂本は時の大御所作家である漱石に褒められたことが嬉しく、朝日新聞の切り抜きを後生大事に取っておいたそうです。海辺にホルスタイン種の牛が一頭描かれているシンプルな作品で、牛というモティーフを描くことはフランスへ渡るきっかけとなった、と坂本は語っています。クライスト丸に乗船し3ヵ月かけてフランスへ到着し、パリに暮らし始めました。
エメラルド・グリーンを含むパステル調の登場
拠点こそパリに定めましたが、むしろブルターニュ地方を中心としたフランス各地へ赴き滞在し制作しました。《キャンペルレ(湖畔の牛)》(no.2)もそのうちのひとつです。《うすれ日》(no.1)とは異なる種類の乳牛や、単純化された建物や煙突に加えて、湖面にも注目してみましょう。エコール・ド・パリの画家が活躍していた頃のフランスで、坂本はエメラルド・グリーン調をひとつの傾向として打ち出すようになります。パリ6区にある美術学校グランド・ショーミエールのモデル市で目を付け、その相貌に惹かれて雇ったモデルを描いた《老婆》(no.3)の背景にも同傾向の色が見て取れます。老婆の着用している服装はブルターニュ地方の「コワフ」と呼ばれる民族衣装と考えられます。
牛から馬へ
フランスから帰国後、東京へ戻らず故郷の八女に拠点を構え、ここで終生制作することになります。九州の馬にほれ込み馬市を見に行くうち、牛に代わり今度は馬を描き始め、やがて坂本の代表的なモティーフとなります。《二仔馬》(no.4)の背景の空にはエメラルド・グリーンが面で塗られ、それを背にした馬体や足元に広がる大地の草にも要所で用いられています。馬という対象の形態を坂本独自の感覚で把握し、単純化し描き出しています。
第二次世界大戦が始まると馬は戦争に取られ、モティーフとして描くことが難しくなり、身近なものを題材とした静物画に切り替えて描くようになっていきます。
《林檎と馬鈴薯》(no.5)は、タイトルにある通りの典型的な静物画ですが、球形の林檎や凹凸のある馬鈴薯を描く際に坂本の「らしさ」が強調されています。影の付け方、色の塗り方、全体の色調とのバランスなど…よくみるとエメラルド・グリーンのような色もわずかに使われているようですが、前面には出てこなくなりました。絵画における色と形を裏付けるために必要な存在感、理屈抜きで見るひとに通じるものを「物感」という言葉を使って表現しています。
能面
三木露風との交流から能楽堂へ通ったことがあり、戦後に能面を描くことが増えてきます。床の上に置かれた能面が多い反面、《壁》(no.6)では淡いピンクの壁の上に能面がかけられているのか、あるいは箱から飛び出した能面が浮遊しこちらを見ているようでもあります。単に西洋の影響を受けるだけではなく、坂本の日本的なものの探求でもあり、幽玄の世界が描かれています。
花を描くことも
坂本が花をモティーフとして描くのはとても珍しいことです。《静物》(no.7)には椿のような花が五輪、謠本か砥石の上に、奥には枝や蕾のようなものがいくつか描かれています。1952年の第17回清光会展に坂本が出品した《椿》という題名の板絵の存在が記録されています。
公式ブログトップへ


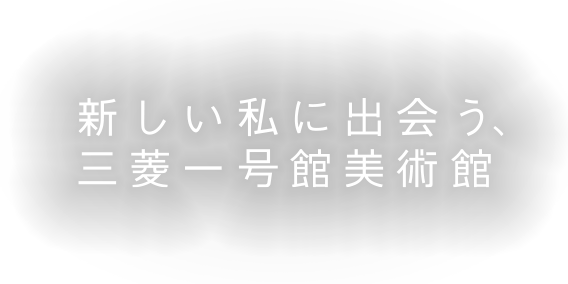







 Ticket
Ticket
 BLOG
BLOG


