丸の内の象徴を復元した
「館(やかた)」としての美術館
内藤 廣
日本近代建築の父と呼ばれたジョサイア・コンドルが設計した三菱一号館は、明治の近代化の象徴として丸の内発展の起点となった最初の「西洋賃貸オフィスビル」。
かつて「一丁倫敦」と呼ばれた土地の記憶をとどめる建築が、三菱一号館美術館としてよみがえりました。
その復元の意義と可能性について、これまで博物館・美術館の建築も、多数手掛けた経験を持つ建築家にお聞きしました。
未来に向けて場所の記憶をとどめる三菱一号館美術館。
建築には、それが存在する場所の記憶の「縁」としての役割という一面があります。 三菱一号館美術館は丸の内再構築計画の一環として、丸の内最初のオフィスビルであった三菱一号館を復元し、美術館として活用しているものですが、もし、この復元がなかったとしたら、結構つまらない街になっていたのではないかと思っています。
都市の再開発というのは往々にして所在なげなもので、超高層ビルを建てて終わりというのが一般的ですが、丸の内近辺の開発は他の場所と少し違っています。 東京駅の駅舎をはじめ、日本工業倶楽部会館や第一生命館(現・DNタワー21)といった、その場所の記憶をとどめる建築をできるだけリスペクトしていこうという考えが垣間見えます。 それを最も典型的な形で表現したのが三菱一号館の「復元」だと思います。
三井が日本橋を中心に江戸文化をパトロネージしたのに対して、三菱は明治以降の東京の近代化をパトロネージしたと言えます。 その象徴となるのが、赤煉瓦造りの三菱一号館です。 あれはどう見ても「江戸」ではなく、「東京」です。 もともと、あの辺りには陸軍省の兵営や練兵場が置かれていたのですが、民間に払い下げられることになり、それを取得したのが三菱でした。
明治政府が推し進める東京の都市計画の一つとして、丸の内一帯の商業地化が計画されましたが、皇居前のこの場所に、明治の日本経済の近代化を支える礎をつくらなければならないということで、三菱は煉瓦造りや石造の建築からなる英国を手本とした近代的な洋風の街づくりを進めたのだと思います。 その意味で、三菱一号館は明治以降に三菱が果たした役割をイメージさせる建築として最適だといえるでしょう。 あの場所に、あの形で、この時代に復元されたということの意味は大きいと思います。
周囲に超高層ビルがニョキニョキと建っているなかで、三菱一号館美術館のたたずまいにはある種の違和感がありますが、この建物があることで、たとえば50年たったとしても、この場所がどういうところだったのかということを思い出す手がかりになるし、逆に新しくできたものが生きるという感じがします。 復元にあたっては、いろいろな手法があったと思いますが、当初の設計、建材、工法に忠実な今回の方法がよかったのではないでしょうか。

美術館が求められている役割を再認識するために。
美術館というものは、名称そのものを含め、大きく見直される時期に来ているのかもしれません。 岡倉天心が明治の末頃に、「せめて美術品を展覧し得る恒久的な建物があればわが国の美術がもっと発展するものを」と書きましたが、この国の美術館の始まりはそこからです。そうした歴史を辿り、現在、公立の美術館は、美術館というよりは「大きな貸しギャラリー」になってしまっている例も少なくありません。 ハイスペックな空調や調光設備を有した極めてニュートラルなホワイトキューブの空間で、管理や運営上、そうならざるを得ない面もありますが、それをほんとうに美術館と呼べるのか。
そもそも展覧するということ自体、つまり絵をたくさん並べて見せること自体が、実は奇妙なことだと僕は思っています。 これは極端な例ですが、僕が展覧会に行く時は、好きな一点に巡り合うために美術館に足を運びます。 作品を豊富に揃えないと入場料を取れないと思っているからかもしれませんが、多くの美術館は並べすぎですよ。 一点だけでもいいじゃないですか、それがほんとうに素晴らしいものであるなら。 その一点との一瞬の出会いを創造するために美術館という建物が存在するくらいでもいいと思いませんか。
人間の体というのは不思議なもので、美術館に足を踏み入れた時と、絵に辿り着いた時とは、体として違う状態であるはずです。 作品に巡り合うということは、そうした身体的な行為も含むはずで、そのデリケートな瞬間をどう演出するかという点からいっても、美術館というのはほんとうに難しい。
さらに言えば、そもそも「美術館」というものはほんとうに必要なのか、もっと言うと、「美術」はほんとうに必要なのかという問題提起もあり得るのではないかと思います。 この先の時代がどうなっていくか分かりませんが、これだけコンピュータと情報社会の世の中になってくると、内発的な感情の吐露として、つまりは人間存在の発露の表現としての「美術」はあったほうがいいのではないか。 今生きている人間のことをどこまで深く考えられるかが、これからの美術館の存在意義だと僕は考えています。 世の中に、精神的にこれだけ不幸な人がたくさんいるなかで、そうした人々をどうやったら救えるか。 これからは、そういう心の問題を美術館という場所も問われるようになるのではないでしょうか。
「館」という個性を持った美術館として、もっと居直ってもいい。
僕は三菱一号館美術館で開催された展覧会は、半分くらいは見ていると思います。 使い勝手ということに関しては、もとの建物がオフィスビルであるという性質を踏まえると、確かにいろいろと感じることはあります。 持ち込める作品の大きさだとか、絵を見る距離だとか、制限の多い一号館美術館の空間ならではの事情を、館の人たちがすべて分かったうえで展覧会を企画しているという丁寧さを感じます。 運営側としてはご苦労も多いと思いますが、何でもできるということは、かえって陳腐化してつまらないものになってしまうのかもしれません。
三菱一号館美術館の場合は「館」という言葉が適切だと思いますが、自分の館に作品を展示するという特殊性があります。 その分、かえって良い印象を持っています。 現在のギャラリー化した公立の美術館から見たら、最も遠い位置にあるのが三菱一号館美術館だと言えるかもしれません。 その意味で、三菱一号館美術館は、もっと居直ってみてもいいのではないでしょうか。 館の亭主が、これ以上ないほど愛している作品を一点だけ、一番いい部屋で、一番いい状態で見てもらうために、その館のすべてがあるという演出も面白いと思います。
ほとんどの美術館が系統展示で、順路に従って鑑賞するという仕組みになっています。 ほんとうにそれでいいのかなと思ったりもします。 スタッフの人に白い目で見られているかもしれませんが、僕は順路を逆から見ることも多いのです。 画家が死ぬ間際に描いた作品から見て行ったほうが面白い場合もありますから。 その芸術家の作品系統を知りたければ、カタログを見ればいい。 実際に美術館で絵を見るということは、そういうこととは異なる次元なのではないだろうかとも思います。 難しいとは思いますが、一度、三菱一号館美術館でも順路を設定せず、「ご自由にご覧ください」とやってみてはどうでしょうか。
美術館で順路に従って鑑賞するということは、見る側からすれば「受動的」であり、自ら何かを発見するという意味での「自発的」な行為を奪っていると考えることもできます。 見に来てくれた人が自ら何かを「発見する」のと、「発見させられる」というのとでは、大きな違いがありますよね。 僕自身の体験を振り返っても、やはり記憶に残っているのは、自分から何かを見つけ出した時です。
三菱一号館美術館の建物のたたずまいには、そうした自発的な発見をする可能性を感じます。 逆に言えば、三菱一号館美術館の学芸員や関係者がそのことに自覚的になり、これから企画する展覧会をプロモーションできるかどうか、つまり公的で一般的な美術館とは違う見せ方ができるかどうかが、今後とても問われるのではないかという気がしています。
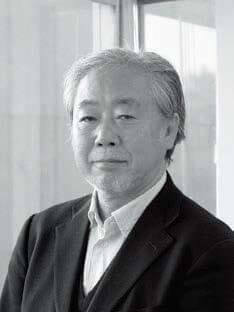
【プロフィール】
内藤 廣
NAITO Hiroshi
1950年生まれ。
早稲田大学大学院修士課程修了後、フェルナンド・イゲーラス建築設計事務所、菊竹清訓建築設計事務所を経て、1981年内藤廣建築設計事務所を設立。
2001~2011年東京大学にて教授、副学長を歴任。
主な建築作品に、鳥羽市立海の博物館、牧野富太郎記念館、島根県芸術文化センター、富山県美術館、高田松原津波復興祈念公園 国営追悼・祈念施設等。